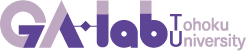【重要】ゲノム編集技術を用いた実験に関する届出方法の変更等について
ゲノム編集技術を用いた実験に関する届出方法の変更等について
〔2019年8月28日掲載〕
ゲノム編集技術を用いて得られた生物(*外来の核酸を含まない場合)についての手続きが変更となります。
*外来の核酸を含む場合には従前通り遺伝子組換え生物としての取扱いとなります。
下記の通りご対応をお願いいたします。
■新規にゲノム編集技術を用いた実験を開始する場合(拡散防止措置の執られた施設での使用等)
→遺伝子組換え実験計画書を申請してください。
ゲノム編集技術を用いた実験に関する届出書については受付停止いたします。
■ゲノム編集技術を用いた実験に関する届出書が受理されている場合
→新規に遺伝子組換え実験計画書を申請するか、承認されている遺伝子組換え実験計画書にゲノム編集生物を追加する変更申請をすることで、届出書からの切り替えを行ってください。申請締切は2019年10月31日(木)となります。
なお、すでに受理されている届出については9月末までにメールにて順次個別にご連絡いたしますが、メールアドレスの変更などにより連絡がない場合には遺伝子実験センターまでお問い合わせください。
■開放系における使用等(拡散防止措置の執られた施設以外での使用等)
→実験計画を検討している場合には、事前に遺伝子実験センターに連絡をしてください。
■ゲノム編集技術を用いて得られた生物の譲渡・譲受について
→遺伝子組換え生物等の譲渡等申請、遺伝子組換え生物等の譲受に関する情報提供内容報告を行ってください。なお、譲渡の際には情報提供書が必要となります。
学内限定 譲渡等申請の記載例はこちら
- 学内限定 (学内通知)ゲノム編集技術を用いた実験に関する届出方法の変更等について(doc:36KB)
- 学内限定 (文科省通知)研究段階におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る留意事項について(PDF: 285KB)
- 学内限定 (参考)ゲノム編集生物のカルタヘナ法上における取り扱い(PDF:108KB)
Q&A
ゲノム編集による一塩基欠損、変異についても申請が必要ですか?
ゲノム編集技術をもちいて得られた生物についてはすべて申請が必要となります。
ゲノム編集において精製タンパクを直接細胞に導入するのですが得られた生物について申請が必要ですか?
本学においては遺伝子組換え実験計画書の申請が必要となります。
ゲノム編集において修復⽤鋳型DNAは使⽤せず、人工ヌクレアーゼによる切断の後の自然修復で変異を作出する予定ですが、申請が必要ですか?
本学においては遺伝子組換え実験計画書の申請が必要となります。
ゲノム編集技術を用いて得られた培養細胞について申請が必要ですか?
細胞についてはカルタヘナ法における「生物」に該当しないため申請は不要です。ただし、その細胞を動物に移植した場合には申請が必要です。
他機関より譲渡を受けた生物の情報提供書に「外来配列の挿入がない」ことが記載されているのですが
ゲノム編集技術をもちいて得られた生物である場合、本学においては遺伝子組換え実験計画書の申請が必要となります。ただし、作出方法がゲノム編集技術ではない場合この限りではありません。